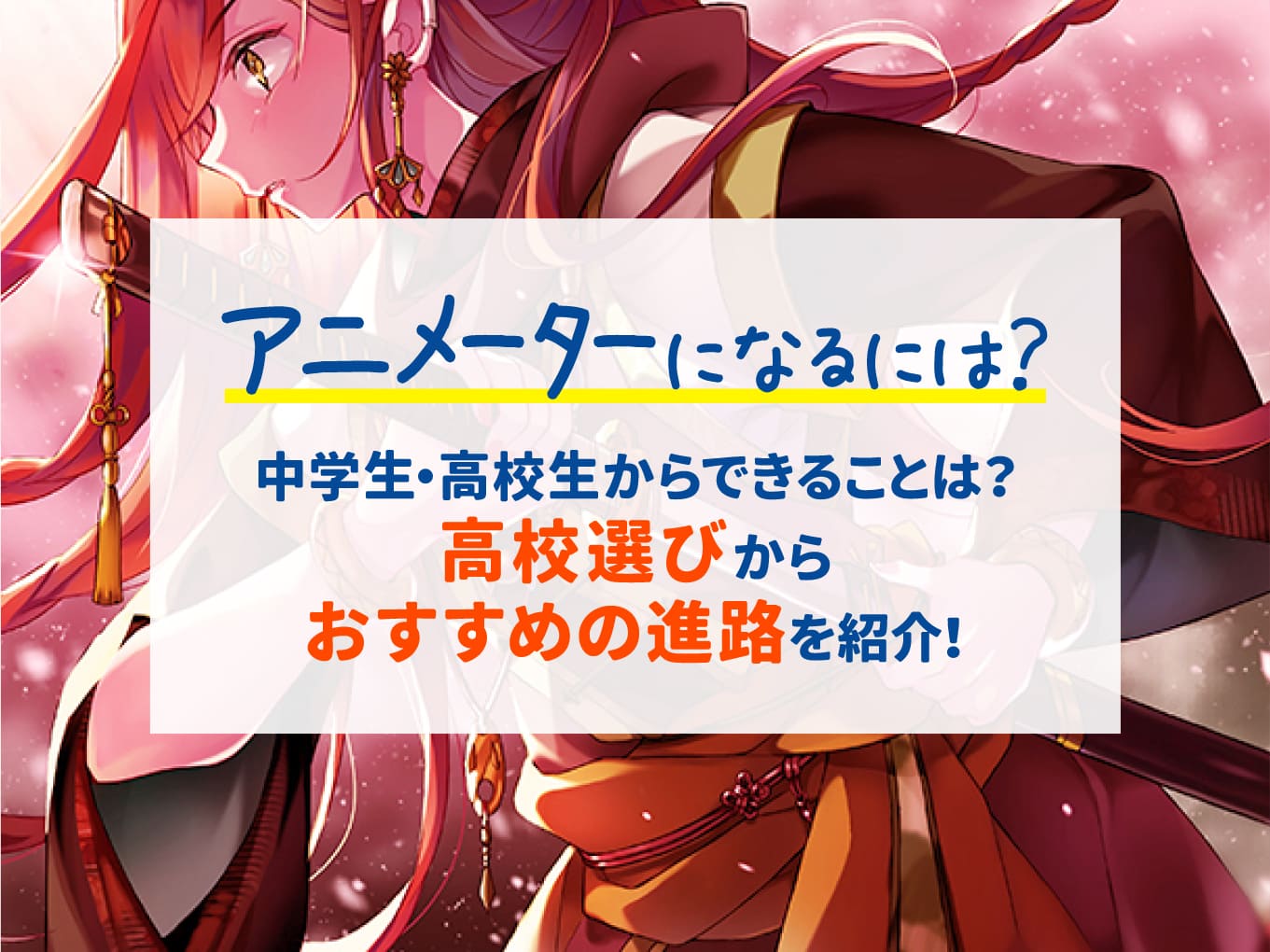
アニメーターは、静止画を主に扱うイラストレーターとは異なり、複数の静止画を連続で描き「動き」をつくりだす作業となります。絵に命を吹き込む仕事とも言われています。日本は世界に誇るアニメーション大国。この記事では、アニメーターになりたい中学生・高校生向けに、今からできることや高校選び、アニメーション制作会社に就職などの進路まで、具体的な情報を紹介していきます。
アニメーターの仕事内容とは?
アニメーターの仕事は、アニメーション制作において作画という重要な役割を担っています。作画は主に原画制作と動画制作に分かれます。近年では他にCGアニメの制作も多く、リアルな動きを再現できるCG制作の仕事もあります。
原画制作
原画制作とは、絵コンテやレイアウトをもとに、アニメの動きのポイントとなる絵を描く作業です。アニメのキャラクターや物体を動かすなかで特に重要な絵を担当するため、アニメの完成度や評価に大きな影響を与えます。原画マンや原画家と呼ばれ、アニメーターのポジションの中でも憧れのポジションのひとつです。原画マンになるには、動画マンとしての経験が不可欠で、常に高クオリティーかつスピーディーに原画制作を行う技術が求められます。
動画制作
動画制作とは、アニメーション制作工程において、原画マンの描いた原画と原画の間をつなぐ「中割り」と呼ばれる絵を描く作業です。絵をつなぐことでアニメに動きを与え、キャラクターに命を吹き込むポジションは、アニメーション制作を陰ながら支える役割を担っています。動画マンや動画家と呼ばれ、アニメーターとしてまず最初に担当するポジションです。経験を積むことで原画マンなどのポジションを目指すことができます。
CG制作
アニメにおけるCG制作とは、コンピューターグラフィックス(CG)の技術を用いて、2Dや3Dでアニメーションを制作する作業です。3DCG空間内でキャラクターや背景、小道具などを立体的に造形するモデリングや、立体物の質感を表現するために貼り付けるテクスチャなど、様々な効果により美しくリアルなアニメーションを制作します。3DCGに関する幅広い知識や最新ツールの操作技術などが必要です。
その他、原画マンとして経験を積むと、絵のクオリティをチェックする作画監督を目指すこともできます。
アニメーションはどうやってできる?アニメーターの仕事の流れを解説!
アニメーターの仕事は、大きくは前述の原画マン・動画マンの作画作業になりますが、アニメーションがどうやってできあがるのか、アニメーション制作の全体の流れを把握しておきましょう。
企画・脚本
制作会社や放送局、スポンサーなどの関係者が集まり、作品のコンセプトやシリーズ構成、スタッフの人選や制作費などをまとめます。そしてシナリオライターが脚本を執筆し、セリフなどの細かい設定は監督などが修正を入れていき、構成が完成します。
各種設定
キャラクター設定やキャラクターが使う物を決める小物設定、機械やロボットなどのメカ設定、背景に関わる部分のデザインを決める美術設定など、美術監督や専属の美術設定スタッフが担当し、作品全体の美術プランを決定します。作品の世界観を決める基板となり、この設定資料がアニメ制作に関わる大勢の人にイメージとして共有されます。
絵コンテ
監督や演出家がカット割りやカメラワークなど検討し、脚本のイメージをビジュアル化したものが絵コンテです。作品の演出に関わる重要な作業で、アニメーション制作の設計図とも言われています。
レイアウト
絵コンテで決まったシーンごとの流れを、より細かく具体的に決めていく作業です。1シーンごとの画面構成、人物や物体の配置などを決定します。原画の前に位置する作業で、背景原図と呼ばれることも。原画マンが描き、監督がチェック、修正することが多いです。
原画
ここから作画作業が開始されます。絵コンテや設定資料を把握し、原画マンがアニメの動きのポイントとなる重要な絵を描きます。主にシーンごとに動きの始まりの原画と終わりの原画を描き、動きの指示書にあたるタイムシートも制作していきます。作画監督がチェックを担い、修正をして清書となる原画が仕上がります。
動画
動きの始まりの原画と終わりの原画の間をつなぐ「中割り」と呼ばれる絵を描いていく作業です。動きを何コマで表現するか決定し、原画をトレースして、少しづつ動かした絵を描いていきます。一枚一枚絵を描いて重ねることで、まさにパラパラ漫画のようにキャラクターや物体に動きがつき、アニメとなっていきます。従来通りのアナログ作画からパソコンやタブレットを使ったデジタル作画まで、アニメーション会社や作品によりその手法は異なります。
彩色
完成した動画(アナログで描かれた場合スキャンした画像)に色をつけていく作業です。かつては手作業で彩色していましたが、現在はパソコン上でのペイントソフトによる彩色がほとんどです。背景画も同様に彩色していきます。
撮影
動画や背景画など、素材をひとつに合成してアニメーションの1シーンを制作し、さらにCGを使って特殊効果を加え、1シーンごとに完成させる作業です。現在この工程はパソコン上で進められていますが、かつて1コマずつ撮影していた名残で、今も撮影と呼ばれています。
編集
それぞれあがってくる1シーン1シーンを、脚本に沿って順番につなぎ、微調整をして1本の映像にまとめる作業です。
アフレコ・音響
アニメの映像に合わせて、各キャラクターを担当する声優がセリフを吹き込みます。同時進行でナレーターの声や音楽、効果音も制作され、映像と音の組み合わせによってアニメが完成します。
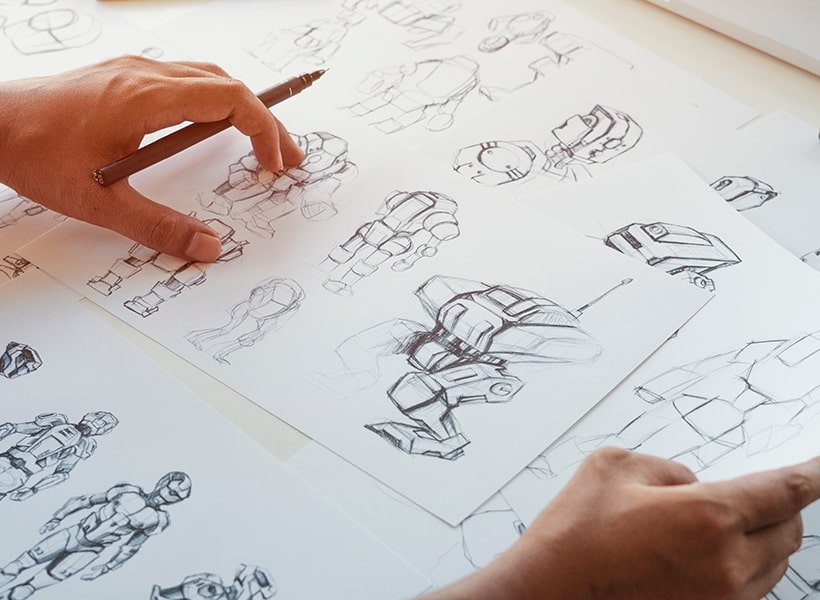
アニメーターになるために必要なスキルは?
膨大な量の絵を描き続けるアニメーターになるためには、画力はもちろん、スピードや忍耐力など様々なスキルが必要です。求められるスキルを知り、今からできることに取り組んだり、学べる場所を検討したり、今後の進路を考える参考にしてください。
デッサン力
デッサン力は、アニメーターに最も必要なスキルと言えます。対象をじっくり観察することにより、本質的な構造を理解し、物の形を見たままに正確に描き取ることが大切です。描写力、表現力、バランス感覚など、絵を描く基本スキルを養います。さらに、アニメーターは写実的な描写・表現だけでなく、非現実的なシーンをリアルに描くスキルが必要です。そのような頭の中で思い描いたイメージを具現化するために、基礎であるデッサン力の習得は必須です。
画面構成力
画面構成力は、キャラクターや物体、背景の配置を計算し、空間の使い方によって視聴者の感情や注目点を自然にコントロールするスキルです。ストーリーテリング(物語を使って表現すること)の重要な要素で、シーンの緊張感や雰囲気を伝えるアニメーション表現の核となります。画面構成力を身につけるには、細かいところまで描き込まなくてもよいので、視聴者の目線に立ったレイアウトのラフを毎日描いて感覚を高めていきましょう。
空間把握能力
空間把握能力とは、空間にある物体の位置や形、大きさ、方向などを認識する能力です。空間認知能力や空間認識力とも呼ばれます。アニメーターは、空間を認識してキャラクターや物体を立体的に表現し、アニメーションのリアリティと魅力を高めます。そのためには消失点や目線の高さなどを意識して、平面に奥行きを持たせるスキルが求められます。物体をどの角度からでも自由に頭の中でイメージし、それを平面のイラストに表現できるようになるには、幅広い分野のイラストを描き込み鍛錬を重ねる必要があります。
観察力
アニメーターには、人や物の動きや構造を捉える観察力が求められます。人の表情や動作の観察力を養い、パーツ位置や立体の繋がりを理解することで、キャラクターの心情や動作を絵で表現する際に役立ちます。植物や建物などの構造を注意深く観察することも、空間や背景を描く際に生かすことができます。
スピード
アニメーションは、1秒間に24コマの絵が切り替わり動画となるため、膨大な絵を描く必要があります。アニメーターは絵が上手いだけでなく、スピーディーに描ける能力が必須です。膨大な数の作画をこなすために、アニメの世界観を損ねないクオリティの高さを保ちつつ、効率的に描くスピード感が求められるため、アニメーターを目指すのであれば、毎日絵を早く描く練習をしましょう。
柔軟性
原画マンや動画マンは、絵を描く際に監督のイメージを表現できるよう、監督や仲間の意見を柔軟に取り入れることが必要です。作品全体を視野に入れ、臨機応変に修正しながら、よりよい作画、最終的にはよりよい作品を目指して、仲間とともにがんばれる柔軟性を身につけましょう。
コミュニケーション能力
監督や作画の先輩など、相手の要望や意見を正しく理解し、それを絵に表現していく必要があるため、コミュニケーション能力は必要です。特別に高いコミュニケーション能力が求められるわけではありませんが、アニメーション制作は多くの人が携わる現場です、協調性を持ち円滑なコミュニケーションを行えるよう、今から他者との会話など気を配ってみましょう。
デジタルツールの操作能力
3DCGアニメでなくとも、近年はアニメーション制作でデジタル技術を導入している工程は多く、デジタルツールやソフトの操作スキルが求められます。ペンタブレット、液晶タブレットなどのツールや、Photoshop、CLIP STUDIO PAINTなどのソフトは自分でも購入できますが、実践的な使用方法を学べる学校などで用意されていますので、専門的に教わったほうが習得は早いでしょう。

アニメーターになるのに資格はいる?
アニメーターになるために必要な資格はありません、とにかく画力で勝負の世界です。就職時に資格を求められることはほとんどありませんが、スキルの証明に使うこともできますので、個人でも受験できる資格をご紹介します。
アニメーション実技試験
アニメーション実技試験は、CG-ARTS(公益社団法人画像情報教育振興協会)が主催する、将来アニメータを目指す学生向けの試験です。課題の指示を正確に読み取り、CGアニメーションを制作することで実力を評価します。
CGクリエーター試験
CGクリエーター試験は、CGで表現するデザイナー、クリエイターのための検定で、アニメーション実技試験と同様にCG-ARTS(公益社団法人画像情報教育振興協会)が主催。デザインや2次元CGの基礎から、構図やカメラワークなどの映像制作の基本、 モデリングやアニメーションなどの3次元CG制作の手法やワークフローまで、 多様な知識が出題されます。知識の理解を測る「ベーシック」と知識を応用する力を測る「エキスパート」に分かれています。
色彩検定®
色彩検定®は、公益社団法人の色彩検定協会が主催・認定する、色に関する幅広い知識や技能を問う検定試験です。1級から3級までの3段階に分かれおり、公式テキストに準拠した内容で出題され、色彩やデザインについての専門的な知識や実務経験は必要ありません。センスやアイデアを問うものではなく、公式テキストの内容をしっかりと理解すれば、これまで色彩を学んだ経験のない方でも合格できる検定です。
アニメーターに向いているのはどんな人?アニメーターの5つの適正を解説!
アニメーターになりたいけれど、自分なれるのか不安な人もいると思います。アニメーターに向いている人の適性をまとめましたので、参考にしてみてください。
絵を描くのが好きな人
何よりアニメが好きで絵を描くのが好きという気持ちが大切です。アニメーターは作品や担当によっても異なりますが、月に何百枚、何千枚ものイラストを描く仕事です。毎日絵に向き合っていても苦にならない、それを楽しいと思える人がアニメーターに向いています。
根気強くコツコツと作業できる人
作画作業では、1コマ1コマ丁寧に絵を描いていきます。似たような構図を描き続けたり、細かい修正を繰り返したりと、毎日地道な作業を続けられる根気強さが必要です。自分の携わったアニメが完成することをモチベーションに、常に絵と向き合い続けることができる人が適任です。
責任感のある人
アニメーターの作業には締め切りがあります。納期を守るために、責任感を持って周囲と連携しなければなりません。アニメーション制作はチームワークが重要で、納期に遅れると他のスタッフの作業に影響が出てしまいます。自分の仕事は、期限内にしっかりとやり遂げられる責任感のある人に適しています。
向上心のある人
スムーズに作業を進めるため、そして何よりよい作品をつくるには、クオリティの高い画力が必須です。周囲に求められるアニメーターになるためには、安定して絵を描き続けられる根気強さやタフさはもちろんのこと、現状に満足せずに日々の努力を怠らない向上心が必要です。
人と協力して何かをするのが好きな人
アニメーターはひたすら絵を描き続けるイメージを持っている人もいるかもしれませんが、アニメーション制作には多くの人が携わっており、各工程のスタッフと連携して行われます。そのためスムーズに作業を進めるには、各スタッフとの協力が必要です。現場で円滑な人間関係を築き、仲間と協力して作業することに楽しみ見出せる人はアニメーターに向いています。

アニメーターになるまでの道のり
アニメーターになるには、学校などで絵やイラスト、漫画、アニメに関する技術を学び、アニメ制作会社に就職するのが一般的です。フリーランスのアニメーターという働き方もありますが、アニメ制作会社で実務経験を積んだ方がほとんどです。アニメ制作会社に就職するには一般企業と同様で新卒採用、中途採用の求人募集に応募します。採用試験では書類選考、面談、作画試験が行われています。総合的な画力を認めてもらう必要があるため、正直独学での就職は厳しいです。アニメ制作会社に就職するためにはどこで学べばよいのかなど、それまでの道のりや選択肢をご紹介します。
アニメーター養成所に入所する
アニメーター養成所とは、アニメーターの技術を次の世代に伝えることを目的とし、主にアニメーション制作会社が運営しています。それぞれの制作会社の直下にあるため、各制作会社でプロのアニメーターとして働くための、原画演習などの技術を学ぶことができます。多くの養成所の年齢制限は高校卒業後の18歳から25歳までで、募集人数も少数です。未経験者には難関であるため、まずは画力を磨いてから挑戦しましょう。
美術系の大学に通う
アニメーターは画力で勝負となりますので、美術系の大学でデッサンをはじめ各種絵画など、絵を描く技術を体系的に習得することで実力を伸ばすことができます。4年間でじっくりと腕を上げて、就職活動に挑むことができます。アニメーターの募集は養成所なら18歳から25歳までとなりますので、大学卒業の時点で22歳となり、年齢制限に問題はありません。
専門学校に通う
専門学校は専門的な分野に特化して知識や技術を学ぶ学校です。アニメーターを目指すのであれば、絵を描く技術を習得できるアニメーションコースやイラストコースのある専門学校を選びましょう。現役のアニメーターやイラストレーターの講師陣や本格的な設備、業界との繋がりによるサポートなど、専門的な教育環境が充実しています。専門学校で2年間学んでから、養成所への入所や制作会社への就職を目指すことができます。
通信制高校に通う
専門学校よりもさらに早くアニメーターへの道を歩むことができるのが、アニメーションコースやイラストコースのある通信制高校です。専門学校と同等の教育・設備が整う通信制高校なら、高校生のうちに実践的な授業を受けることができます。アニメーターとしての専門的な技術を身に付けるのに若いに越したことはありません。むしろアニメーターには作画スピードが求められるため、若い人材が必要とされています。高校生という早期に挑戦できる環境は、大きな武器となります。

中学生・高校生からアニメーターを目指すのにおすすめの進路は?
イラスト・芸術を学べる高校への進学がおすすめ
現在中学生・高校生の時点でアニメーターになりたいと考えているのであれば、アニメーションコースやイラストコースなどがある芸術系の通信制高校がおすすめです。アニメ制作会社に就職するのは、大学卒業後なら22歳、専門学校卒業後なら20歳、通信制高校卒業後なら、なんと18歳。10代のうちにアニメーターとしてのキャリアをスタートできます。憧れの原画マンや作画監督も、若くして目指すことができます。
早くからデッサンなどを学んで画力の向上ができる
高校生から絵画やイラストを学ぶ最大のメリットは、いち早く専門的な知識・技術を身につけられることです。独学での画力向上には限界があります。プロの講師陣による指導により、デッサンをはじめとする絵画の技法や、デジタルツールの操作方法などを習得しましょう。専門学校と同等の設備が整う通信制高校では、デジタルイラストを学ぶ環境ももちろん整っています。アニメーターに必要な総合的な実力を磨いて、アニメ制作会社への就職を目指しましょう。
多くの時間を絵を描くことに使える
専門科目が学びのメインとなる通信制高校では、週5日間のうち半分以上が絵画やイラスト制作など専門科目の授業になります。普通科目は登校せずにオンライン授業などを交えて短時間で習学するため、絵に特化した授業に多くの時間を使えます。3年間という貴重な高校生活、大好きな絵を描くことに力を注ぎ、実力をつけましょう。また、通信制高校では全日制と同じ高校卒業資格の取得が可能なため、卒業後の進路も大きく開かれています。多くの通信制高校では普通科目のほか、絵に特化した専門科目も単位認定されます。
進学の他、サポートが充実しているので人より早くアニメ会社への就職も選択できる
専門的な教育を行っている通信制高校は、学校・先生方の進学・就職へのサポート体制が非常に整っていることも特徴です。業界とのつながりや採用情報などが充実しているため、全日制高校と比べて将来を具体的に考えやすい環境です。卒業後は大学・専門学校への進学だけでなく、就職という道を選ぶ人も多いため、進路の選択肢は幅広いです。専門学校では2年しか学ぶことができませんが、通信制高校の魅力は、早期に3年間専門的な勉強ができることです。3年間努力して実力をつければ、アニメ制作会社への就職も夢ではありません。
実際に高校卒業後すぐにアニメーターになった卒業生がいる
実際に高校卒業後に弱冠18際で大手アニメ制作会社に就職した、北海道芸術高等学校の東京池袋キャンパスのマンガ・イラストコースの卒業生の声をご紹介します。
『デッサン、各種イラストの授業など、やっぱり絵を描く授業全般で、ひたすら絵を描いて画力を伸ばしてきたことが今に繋がっていると思います。北海道芸術高等学校に入る前の中学生の頃はたまに絵を描くくらいのレベルでした。自分がちょっとくらい得意なことって絵しかないな、そのくらいの感じだった私が、今はアニメーターの卵としてがんばることができています。
入社したProduction I.Gの同期はみんな大卒以上で、私は最年少です。中学生の時は不登校児でしたが、北海道芸術高等学校で好きなことを自分なりにがんばって、夢に近づくことができました! 早いうちに専門的なことを学ぶことができて、とても良かったと思っています。』

マンガ・イラストコースのあるおすすめ通信制高校「芸高グループ」
芸高グループは、学校法人恭敬学園が運営する北海道芸術高等学校をはじめとする、以下5つの学校(6つのキャンパス)で構成される、芸術分野の専門性に特化した学校です。
<芸高グループ>
北海道芸術高等学校
札幌サテライトキャンパス
東京池袋サテライトキャンパス
福岡芸術高等学校
東北芸術高等専修学校
横浜芸術高等専修学校
愛知芸術高等専修学校
マンガ・イラストコースは全てのキャンパスに設置されています。未経験でも初心者でも、自信がなくても大丈夫。「絵を描くのが好き、アニメーターになりたい」という気持ちを重視しています。中学校卒業以上であれば入学に年齢制限はなく、いつでも転入学・編入学可能です。中学校卒業後の一般的な4月の入学のほか、現在高校に通っている人も高校を退学した人も、転入学・編入学できます。
6つのキャンパスのうち3つに関しては高等専修学校ですが、北海道芸術高等学校(通信制高校)とのダブルスクール制度を採用することで、全日制と同様の高校卒業資格の取得も可能となっています。そのため、進路の選択肢も広がっていますので、アニメーターを目指して心置きなく絵を描くことに没頭できます。

✅ マンガ・イラストコースに関するこちらの記事もチェック
> 不登校でも高校に行ける!東京でイラスト・漫画を学んで成長できるおすすめ通信制高校
> マンガ・イラストコースではどんなことが学べるの?授業について教えて!(北海道芸術高等学校 札幌キャンパス編)
💬 在校生や卒業生の声はこちら
【在校生インタビュー:Nさん】毎日3時間以上かけて通っていますが、北海道芸術高等学校にして良かった!
【卒業生インタビュー:Yさん】創業100年以上の老舗ゲーム開発会社に入社!進路活動や仕事について教えて!
【卒業生インタビュー:Kさん】作品と共に3年間の成長に迫る!(北海道芸術高等学校 東京池袋キャンパス マンガ・イラストコース編)
参照:北海道芸術高等学校 https://www.kyokei.ac.jp/
※本サイトは、芸高グループの生徒や先生にインタビューを行う機会をいただき、独自取材の記事で芸高グループを応援する個人運営サイトです。
> 生徒たちの様子がわかるInstagramはこちら
この記事をシェアする
